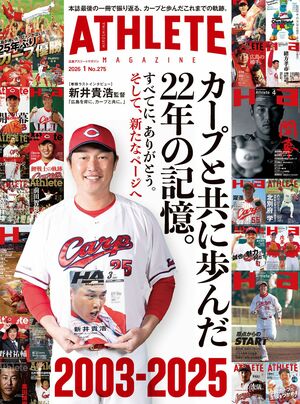4月12日に、東京六大学野球の春季リーグ戦が開幕する。ここでは『最高学府』らしい取り組みで悲願の『勝ち点』獲得を目指す東京大の挑戦に迫る。
東京大学スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI)と株式会社エイジェックは、スポーツ科学分野での連携協定を結び、最先端のデータ分析やバイオメカニクス研究を活用し、選手のパフォーマンス向上とケガ予防に関する研究を行っている。
そんな中、3月18日、東京大(以下、東大)は社会人野球チーム・エイジェックとのオープン戦を行った。この試合で東大の先発マウンドに立ったのは、試合を行った栃木市で生まれ育ち、同市内の國學院栃木高を卒業した『ミスターサブマリン』渡辺俊介氏の息子、渡辺向輝投手。
父譲りのアンダーハンドから繰り出される多彩な投球を武器に、昨年の都市対抗野球にも出場したエイジェックを相手に堂々としたピッチングを披露した。試合はエイジェックが社会人野球の意地を見せて勝利したが、この取り組みは、単なる交流戦にとどまらない。
◆動作解析(バイオメカニクス)を通じ、選手パフォーマンスの向上へ
野球の未来を見据えた共同研究を進めている。両者は脳・神経・筋といった多角的な視点から野球を科学的に分析し、選手のパフォーマンス向上やケガ予防を目指している。
特筆すべきは、東大野球部がエイジェックスポーツ科学総合センターを活用し、選手のデータ測定を実施している点だ。これにより、選手一人ひとりの動作を精密に解析し、課題を明確にした上でフィードバックを行っている。実際にこの測定データは、選手のトレーニングプランの設計や技術向上に役立てられており、チーム力強化に直結している。
さらに、来年度からはバイオメカニクス(生体力学)分野の研究員が同センターに常駐し、より踏み込んだ研究を進める計画もある。投球や打撃フォームを科学的に解明し、最適な動きを導き出すことで、野球におけるパフォーマンス向上に革新をもたらすことが期待されている。
◆膨大なデータから「ベースボールメソッド」を確立へ
エイジェックは『エイジェックベースボールアカデミー』を運営しており、『エイジェックメソッド』という指導プログラムの確立を目指している。この共同研究ではトップ選手だけでなく、ジュニア世代の発達などの分野でも取り組みが行われており、ジュニア選手から社会人、プロなどの熟練者までのデータが蓄積された同センターのデータを元にプログラミングが進められている。
◆ニューロサイエンスの権威が野球界へ本格参戦
共同研究にはニューロサイエンスの権威である東京大・中澤公孝教授も参画し、運動と脳や神経の関係などについての研究も行われる。これらの研究では高いパフォーマンスを追求することはもちろん、『イップス』と呼ばれる、脳のエラー反応が原因で投球動作がスムーズに行えなくなる症状の改善にも改善にも役立てられる計画だ。
東大野球部には、渡辺向輝投手に加え、大学野球日本代表候補に選出された酒井捷外野手、六大学リーグでベストナインを受賞した中山太陽外野手といった将来性豊かな選手がそろう。彼らは、卓越した学問的知見と高度なスポーツ科学のサポートを武器に、六大学野球の“台風の目”として台頭するポテンシャルを秘めている。
今回の試合は、こうした科学的アプローチの成果を検証する場となっただけでなく、両者の協力関係が着実に深化していることを示す象徴的な一戦であった。エイジェックと東大によるスポーツ科学の探究は、今後も野球界に新たな風を吹き込むだろう。