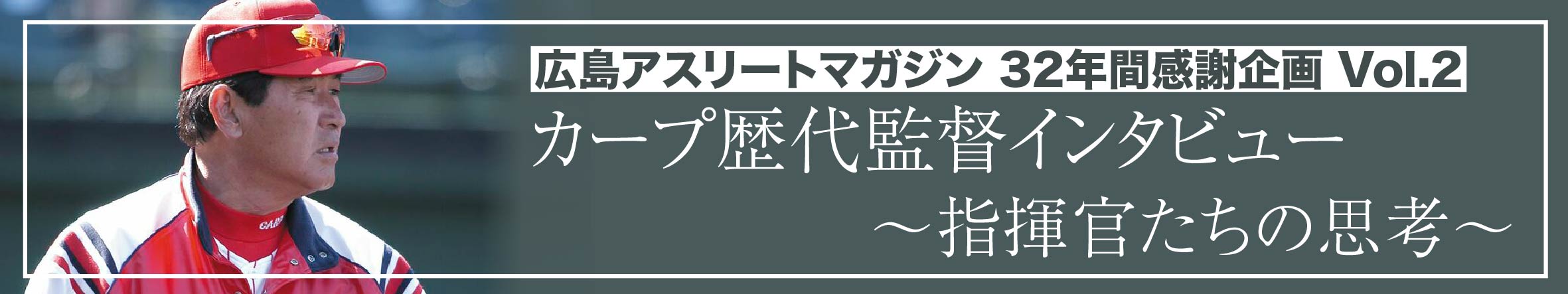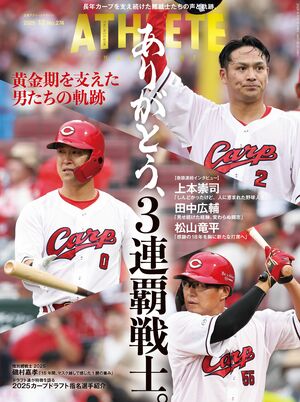1993年の創刊以来、カープ、サンフレッチェを中心に「広島のアスリートたちの今」を伝えてきた『広島アスリートマガジン』は、2025年12月をもって休刊いたします。32年間の歴史を改めて振り返るべく、バックナンバーの中から、編集部が選ぶ“今、改めて読みたい”記事をセレクト。時代を超えて響く言葉や視点をお届けします。
第2回目の特集は、カープ歴代監督のインタビューセレクション。
広島東洋カープを牽引してきた歴代の監督たち。その手腕や采配の裏には、揺るぎない信念とカープへの深い愛情があった。ここでは、広島アスリートマガジンに過去掲載した監督たちのインタビュー、OBによる証言を厳選。名場面の裏側や選手との関係、勝利への哲学など、時代を超えて語られる言葉の数々をお届けする。
今回は、2006年〜2009年までカープを率いた、マーティー・ブラウン監督編(2018年4月号掲載)をお送りする。ブラウン監督のもと、セットアッパーとして復活を遂げた横山竜士氏(現・広島二軍投手コーチ)が当時を振り返る。
◆選手に近い、『同士』のような感覚で接してくれた
マーティーが監督に就任するにあたり、当時ほとんどの選手が外国人監督の経験がなかっただけに『どうやってコミュニケーションを取ればいいのだろう』という雰囲気がありました。当時、僕は山本浩二監督の元で故障続きだったこともあり、プロ野球選手としてこの先もう一踏ん張りしなければならない、という時期でした。
そんな中で迎えたキャンプでは、マーティーからの指示はほとんどありませんでした。投手陣の練習は投げ込みも走り込みもなく、それまでとは練習方法が一気に変わりました。ですが、それまではブルペンで投げ込みを行って調整することがメインで、肩痛を抱えていた僕にとってはリスクが高いものでした。
それだけに、個々の課題を持って調整するというマーティーの方針は僕に合っていました。そして過去の成績、投球スタイルについても、特に指摘されることはなく、横一線で選手たちを見ていたと思います。
マーティーが行ってきた数々の改革の中でも、僕に直結したものが中継ぎ投手陣のローテーション制でした。最大でも2連投すれば、翌日の登板は行いませんでしたし、とにかく投手陣の故障のリスクを回避するというものです。
当時は日本球界で中継ぎの勝ちパターンを形成するチームが増えていた時期でした。それまでカープは誰が投げるかがはっきり決まっていなかったので、マーティーが完全分業制としたことで、リリーフ投手陣は準備がしやすくなり、僕としてもとても調整しやすかったです。