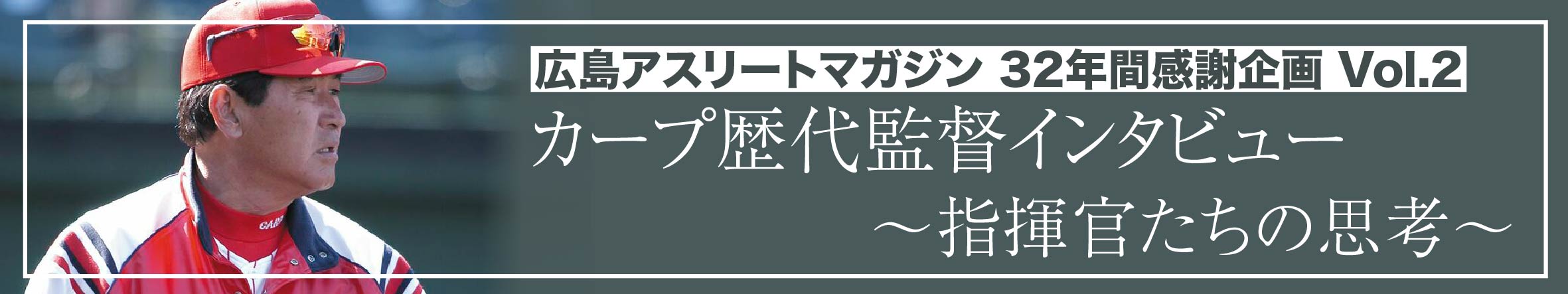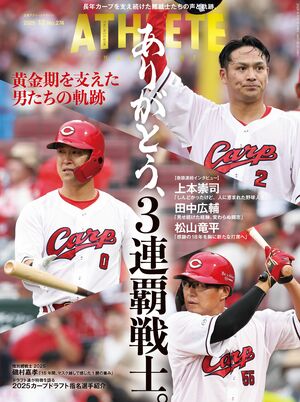◆「俺の扉はいつでも開いている」
またマーティーは「俺の扉はいつでも開いているから、何でも聞いてこい」と、選手に対してオープンなスタンスでした。僕は積極的に意見することも多かったのですが、「四球を気にするのではなく、とにかく球を低めに集めなさい。君たちの役割は低めに投げてゴロを打たせることだ」と言われたことがありました。
それはどういうことかいうと、リリーフは長打を打たれれば失点する確率が高くなる、このリスクを回避するという考えです。また『結果的に四球になったとしても低めに投球すれば、内容は問わない』という方針はとても画期的でした。個人的に直球の勢いが衰えてきた時期でもありましたし、投手としての意識改革、モデルチェンジをする大きなきっかけになりました。
野球でも積極的にコミュニケーションを図る監督でしたが、それはグラウンドの外においても変わりませんでした。時には「みんなでアメリカンフットボールを見よう」と数人の選手を誘ってくれて、一緒に食事に行ったり、お酒を交えて楽しくコミュニケーションを取る機会もありました。
日本的な考えで言えば、監督と選手という間柄でそのようなことは稀なことだと思いますが、そこは外国人ならではの考えだと感じましたし、マーティーに対しては『監督・上司』というよりも、より選手に近い『同士』という感覚で普段から接することができていました。
またファンのみなさんも記憶している方も多いと思いますが、マーティーはベースをぶん投げてみたり、よく退場をする激情型の指揮官というイメージがあると思います。ですが、退場してもベンチ裏では冷静に試合展開を見ていましたし、その行動もすべて、チームを勝利に導くために、選手たちの士気を上げるためのパフォーマンスだったのでしょう。
もちろん、その行動はリスクを伴うものですが、マーティーからは『これで上手くいかなかったら、すべて自分の責任だ』という気持ちをいつも感じさせてくれましたし、選手としてはある意味面白いなと感じました。
結果的にマーティーがカープを率いた4年間は、なかなかチームの戦力が整わず、苦しいシーズンが続きました。ですが、僕個人としては、先に述べたように、プロ野球選手としての考えを変えてくれた良い出会いでした。
もしマーティーに出会っていなければ、投手として若い頃からの理想像を追い求め過ぎ、プロ野球選手としてもっと早く終わっていたと思います。当時の僕にとって、『今の自分の活かし方は何なのか。この先チームに対してどういう立ち位置でプレーしなければならないのか』を考える大きなきっかけになりました。
4年間マーティーの下でプレーをして、合理的な考えを持った、アメリカ版野球小僧な監督だと感じました。そして、あの時期に球場もマツダスタジアムへと変わり、ファンサービスに対する考えも含めて、カープが変化していくきっかけをつくった監督でもあったと思います。