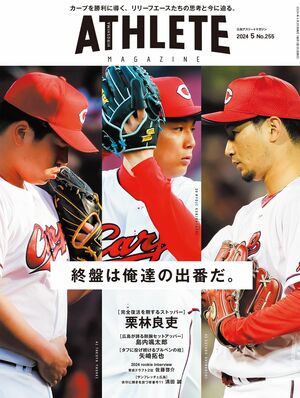2010年から5年間カープを率い、25年ぶりの優勝への礎を築いた野村謙二郎元監督。この特集では監督を退任した直後に出版された野村氏初の著書『変わるしかなかった』を順次掲載し、その苦闘の日々を改めて振り返る。
「変わるしかなかった。」のご購入は、広島アスリートマガジンオンラインショップ
では、選手の頃であれ引退した後であれ、僕は監督という職業を実際はやりたかったのか? その質問に対しては正確に答えることが難しい。というのも、僕は基本的に監督という仕事は「やりたい」と手を挙げてやるようなものではないと思っているからだ。
世の中にはプロ野球チームの監督をやりたい人が数多くいるが、だからといって「じゃあどうぞ」と任せられるものではない―それが僕の監督という仕事に対する考え方だ。そういう意味では、僕には「監督をやりたい」という気持ちはなかった。
しかしそれと矛盾するように思われるかもしれないが、「きっとカープの監督をやるときがくるのだろうな」という気持ちが心のどこかにあったかもしれない。まったく生意気で、思い上がった物言いに思えるが、ある種の使命感のようなものはずっと胸の中にあったのだ。それはある意味、家業を継ぐような感覚に近いだろう。
僕は現役時代、カープという球団一筋で17年間過ごさせてもらった。カープに育てられ、カープで成長させてもらった恩がある。カープの野球をよく知っているという自負もあるし、カープの野球がどこよりも素晴らしいものであるという誇りもある。
僕は“ミスター赤ヘル”である山本浩二さんにも第一次政権(1989~1993年)、第二次政権(2001~2005年)とかわいがってもらったが、その中で何度も「次はおまえがやらんといけんぞ」という言葉をかけてもらった。浩二さんの第二次政権が終わるときに僕も一緒に引退したが、浩二さんに言われた言葉はずっと心に残っていた。