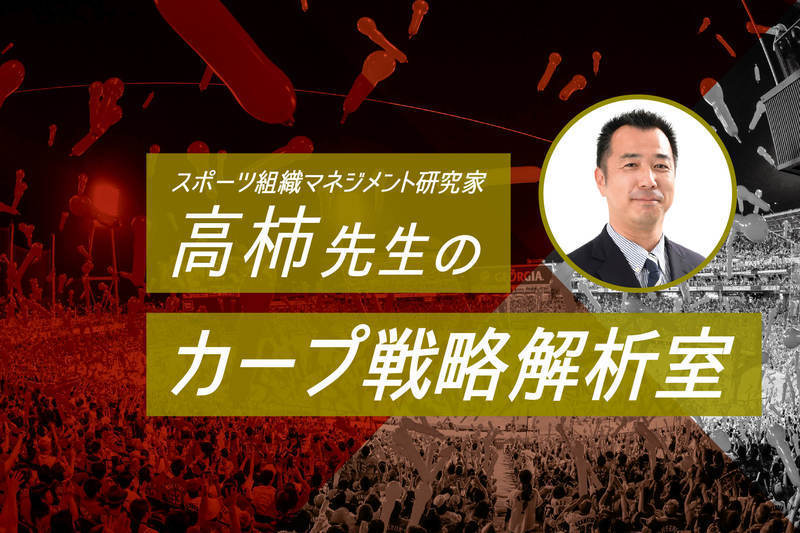組織論・戦略論 などの視点から、近年のカープの強さ・魅力の秘密を紐解いていく、広島アスリートマガジンwebでしか体感できない講義・『カープ戦略解析室』。案内人は、高校野球の指導者を20年務め、現在は城西大経営学部准教授として教鞭をとるなど多彩な肩書きを持つ高柿健。9回目の今回は、カープ野球に刻まれる“粘りのDNA”について考えていく。
終盤の変革への契機
2020年8月5日のヤクルト戦。3-1の2点リードで迎えた8回裏、カープは無死一、二塁のピンチを迎えた。今季、幾度となく見てきた終盤の逆転負けパターンを危惧したファンも多かっただろう。
ここで登板したのが塹江敦哉だ。塹江は青木宣親を三塁ファールフライ、村上宗隆を歩かせて一死満塁とするも、山崎晃大朗、西浦直亨を連続三振に切って取り無失点でこのピンチを切り抜けることに成功した。
9回1点を追加したカープはこの試合を4-1で勝利した。この1勝、いやこの塹江の3アウトは今後のカープの『終盤』を変えるイニングだったのではないだろうか。
塹江の投球は、カープの絶対的守護神であった江夏豊の円熟の投球術とは違う「勢い」と「若さ」のボールであったが、その気迫のクロスボールは私には伝説の左腕と重なって見えた。
今回はカープ野球に刻まれた『粘り』のDNAを解析するために、そのルーツとなる『江夏の21球』を経営学的視点で振り返ってみたいと思う。
1979年(昭和54年)11月4日、近鉄との日本シリーズ第7戦(互いにホームゲームで勝利し3勝3敗での最終戦)。カープは初の日本一を懸けて戦っていた。
カープは初回の衣笠祥雄、3回の水谷実雄のタイムリーヒットで序盤2点リードするも5回、平野光泰(近鉄)の2点本塁打で同点とされる。
その後6回、カープは水沼四郎の2点本塁打で再びリードするもその裏、1点を返され1点差。7回に早くもリリーフエースの江夏豊を投入することとなった。
江夏は7回、8回と抑え、カープは1点リードのまま9回裏を迎えた。語り継がれる『江夏の21球』とはこの最終回に起きたドラマのことである。