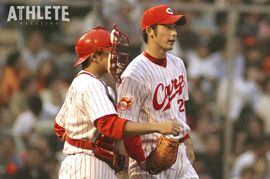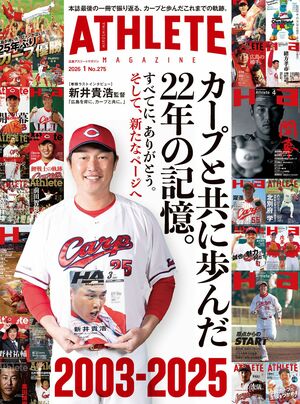長く、カープの野球といえば『機動力』と表現されてきた。バットだけでなく、足もからめた攻撃は、相手チームにとって脅威の存在となってきた。ここではカープにまつわる『赤ヘル機動力のうんちく』を紹介する。(全3回/第2回)
◆カープ黄金期を彩る、古葉野球のはじまり
1953年、松竹ロビンスで二度(1950年、1952年)盗塁王に輝くなど俊足で鳴らしていた金山次郎が、初代監督・石本秀一の要請でカープに移籍した。構想通り1番セカンドとして起用され、攻撃時には足で塁上を賑わせた。
セ・リーグ初代盗塁王に輝いた1950年の74個には及ばなかったものの、カープでも果敢に先の塁を狙い58個で自身3度目の盗塁王を獲得。カープ初の個人タイトル獲得者となった。後に「金山が広島を変えた」と言われるなど、金山こそがカープ機動力野球の基礎をつくった男と言っても過言ではない。
時を経て1963年には後に監督としてカープに機動力野球を植え付ける古葉竹識が、巨人の長嶋茂雄と激しい首位打者争いを演じた。
一時はトップに立ったものの、10月12日の大洋戦で島田源太郎が投じたシュートをアゴに受け負傷退場。オールスターゲームでMVPを獲得するなどシーズン通して好調をキープしていたが、アゴの骨折により土壇場で首位打者を逃してしまった。
死球以降は打席内で腰が引けるなど打撃に支障をきたすようになったため、1964年からは『足』を使ったプレースタイルに軌道修正。スタイル変更が功を奏し、1964年と1968年の二度にわたり盗塁王を獲得している。
死球は不運だったが、この出来事が1980年代前後のカープ黄金期を彩る“古葉野球”の始まりとなった。
(第3回へ続く)