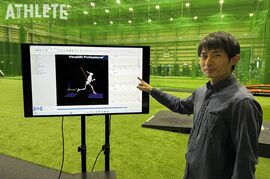2010年から5年間カープを率い、25年ぶりの優勝への礎を築いた野村謙二郎元監督。この特集では監督を退任した直後に出版された野村氏初の著書『変わるしかなかった』を順次掲載し、その苦闘の日々を改めて振り返る。
「変わるしかなかった。」のご購入は、広島アスリートマガジンオンラインショップ
せっかく良いスタートが切れて「今年こそは」という中で、交流戦の10連敗は非常に痛いものがあった。誰もが「何なんだよ……」と苛立ちを見せ、チームに失望感が広がった。僕はシーズンを通した戦い方のイメージとして、オールスターまでは5割をキープ、そして夏場に踏ん張って、秋からスパートをかける―というものを持っていた。
それは僕自身の妄想ではなく、カープという球団の歴史を見ればおのずとわかることだった。カープはこれまでも競って競ってペナントの最後にやっと優勝が決まる―そんな戦いを繰り返してきたのだ。
そのために逆算していくと、夏場は暑い広島で相手がへばっているときにいかに叩けるかが勝負になる。そこへのモチベーションを保つためには、やはりオールスターまで最低でも勝率5割の位置につけていたい。それがシーズン序盤であっけなく崩れてしまったのだ。当時は強気のコメントを出していたが、内心は「ここで正念場がきたか……」と頭を抱えていた。
実は僕は監督を始めてから、すべての試合で手帳にメモをとっている。最初は試合中にスコアや球数、四球などを確認するための走り書きだった。しかし次第に試合中に浮かんだ感情を書き込むようになっていった。「なんで思い切ってサインを出せなかった?」など自分自身に対する怒り、選手やコーチに対する気づき……中にはひどい言葉や憎しみがこもった発言もあり、ページが破れるほどの強い筆致で書かれているときもある。
もちろんそれは誰にも見せられないし、見せるつもりもなかった。だが手帳は重要性を増していく。特に監督1年目は「何やってんだ!」という怒りを外に吐き出していたが、2年目以降はそれを手帳に封じ込めるようになった。感情むき出しで選手と接することを止めたため、怒りの捨て場所がなくなり、「このバカタレ!」などと手帳に書き殴って、バーンと閉じてオシマイにすることが増えたのだ。